「令和4年度 広島市自立支援協議会 安佐南区地域部会 精神障害者部会 講演会」②
- 黒杭 香代
- 2023年2月6日
- 読了時間: 3分
更新日:2023年7月18日
令和4年12月13日(火)19:00~20:30 新型コロナウィルス等感染防止対策を講じて,安佐南区総合福祉センターで講演会を開催しました。参加者は30名で、精神科病院・クリニック、精神科訪問看護事業所、相談支援事業所、行政等の参加がありました。
今年度は精神障害者部会で安佐南区「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム」に取り組んでいます。
「令和4年度 広島市自立支援協議会 安佐南区地域部会 精神障害者部会 講演会」の第一弾として,精神障害者部会の「周知・促進グループ」で企画した,11月16日(水)に地域生活支援センター 原田葉子氏による精神障害の理解促進を目的にした講演会と当事者による体験談を開催しました。
この度の研修会は,その第2弾として精神障害者部会の「ネットワークグループ」で関係者の連携強化を目的に企画しました。
第一部では,「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」について,中山心療クリニック 院長中山純維氏にご講義いただきました。
精神医療の歴史で西洋と日本の変遷について学びました。また、2004年の「精神保健医療福祉の改革ビジョン」で、入院中心医療から、地域医療中心に変更になったという説明がありました。「地域包括ケアシステム」は、元々認知高齢者のためのシステムであり、「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム」に至ったという経緯をお話されました。
また、「包括」は、医療・障害福祉・介護・住まい・社会参加・地域助け合い・普及啓発を包含した意味があることを教わりました。
社会生活を営む上で「自助」・「互助」・「共助」・「公助」があり、地域の助け合いの力の活用の他、様々な関係機関の社会資源を活用すること、そのために関係機関同士の連携を図ることの大切さを学びました。
また、どのように連携して「ネットワーク」をつくればいいのか、中山氏からポイントを教わりました。
・「face to face」の関係づくりや困ったことをお互いに相談する機会をもつ(事例検討等)こと。
・相談場所の広報、人材育成等を行う等「地域生活に関する相談を受ける場所を充実させる」こと。
・地域や企業に対して研修会を開催する等「精神障害者の理解促進」のために活動すること。
アンケートでは、「医療の歴史から地域移行の重要性が理解できました。」「昔と今の比較で地域の精神科医療、福祉の違いが分かりました。」「支援者が生活面等に関して情報共有することで医療側の繋がりをつくり、よりよい支援に繋がる。」等の感想がありました。
第2部では、精神障害者部会の取り組みについて、事務局(生活支援センターあさみなみ)から説明がありました。
第3部では、グループに分かれて、テーマ「福祉の支援者と医療がスムーズに当事者支援を行うために必要な視点」という内容で話し合いをしました。
「自由に意見交換ができて、それぞれの機関の内容を知れる機会になりました。」「このような機会が増えていけば、医療側と福祉側の相互理解が進み、連携がとれやすくなるのではないか。」等の感想がありました。
今回、普段の部会員以外の研修会参加者とのグループワーク実施となり、初めて顔合わせをする方も多々おられました。
機関や職種の特徴を知る機会となり、改めて「顔の見える関係づくり」の大事さを実感しました。
講義で学んだことを活かして、各支援者が日々資質向上に取り組み、今後の課題について引き続き精神障害者部会を通して考えていけたらと思います。
また、精神障害のある方が住みやすい環境づくりとなるよう、関係者同士で顔の見える関係を構築し、地域内のネットワークを強化していきたいと思います。













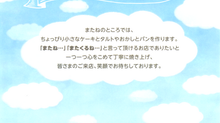































コメント