令和3年度 相談・運営部会④
- 黒杭 香代
- 2022年2月28日
- 読了時間: 3分
令和4年1月28日(金)10:00~12:00 リモート会議で開催しました。
議題は,1.新型コロナウィルス感染拡大による相談支援の現状,2.事務局からの情報提供,3.その他情報交換 でした。
1.については,①相談支援専門員の感染対策,②感染拡大に伴う支援状況等を各部会委員に伺いました。
1月9日からまん延防止棒重点措置となり,各事業所の対応を聴くことで今後の支援の参考にしていくことや,地域の実態を把握することができました。
<相談支援の現状>
・重度障害者が新型コロナウィルスに感染した場合,在宅のヘルパ―が支援に入れないと生死にかかわることや,入院対応が難しい場合がある。
・学校が休校になると,通所サービス等が同時に中止の判断となることが多く,普段利用していたサービスが利用できなくなる現状がある。
・利用者が複数の事業所を併用している場合に,濃厚接触者や該当検査の是非の判断が難しい。
・感染状況に応じて定めている法人内の基準と照らして,支援内容の範囲を検討している。
・基本的にはモニタリング等は電話対応。また,必要性を考えて臨機応変に対応する(感染対策徹底の上で訪問,リモートへの切り替え,個人の面接に絞る,抗原検査実施のタイミングを見極める等)。
・かかりつけ医でPCR検査の受け入れがスムーズにいかない現状がある。
・通所先で陽性が出ていたがヘルパーは中止せず食料が困らないように対応。
・家族が感染して利用者が混乱することがあるため,通所を控えて安静をとってもらっている。
・利用者は元気でも通所休止の場合には自宅待機となったが,幸い問題は生じなかった。
<対応策>
・医療的ケアが必要な障害者が陽性になった際,陰性の家族の付き添いが可能なら入院ができる場合がある。
・在宅支援の際に,完全防備を確実に行い支援にあたることは可能ではないか。
・支援に入れないのであれば代替案を検討することは可能ではないか。
・事業所持続計画(BCP計画)を各事業所ですすめていき,今後の対応策や被害最小化につなげていくことが可能ではないか。
・PCR検査を実施しない病院もあるため実施可能な方法を予め把握する(実施病院に相談等)。
・感染拡大を予防するため,利用者が不調となった場合の連絡窓口を決めておくと良いのではないか。
<地域課題>
・区ごとで保健所で往診を含む訪問の判断基準が異なった⇒保健所や医師会との調整は実施済み。
・広島市はなるべく利用者からの要請があれば支援を断らないようにとの事であるが,
サービス提供事業所によって対応が異なり統一ができていない。
・障害者のヘルパー事業所は介護保険のヘルパー事業所でもあるため,居宅介護事業所との連携や対策を考える必要がある。
・新型コロナウイルスに利用者が感染した場合の問題として,医療機関への入院がひっ迫や入院自体が困難な場合の対応が課題。
・在宅で家族が24時間対応を余儀なくされる場合の対応が課題。
続いて,議題2.については,
①「新型コロナウィルス感染症に伴う臨時的取り扱い」として,広島市に確認済みの相談支援事業所の業務内容に関する特例措置を事務局より資料を用いて説明し,質疑応答を行いました。
②「広島市相談支援事業体制構築の取組進捗状況報告」について,今後3年間の相談支援体制の構想を事務局より説明しています。
・支給決定月変更(成人の利用者の障がい福祉サービス受給者証の更新月を誕生月に変更。令和4年9月更新者から順次変更予定)。
・委託相談支援事業所,基幹相談支援センターの評価基準変更(新基準)による様式変更。
・自立支援協議会に委託相談支援事業所の評価委員を設置し公正な判断をしていく。
まだ案の段階であり,今後検討していき,決まり次第ご報告していきます。
以上,部会内で情報共有したことを基に,今後の相談支援に活かしていきたいと思います。












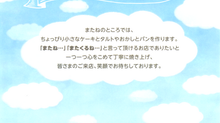































コメント